読書時間:およそ20分。
あらすじ:人間の世界は終わらせました。けど人間は滅びませんでした。再び繁栄しようとサイフォンの森を開拓します。サイフォンに食われれば口減らしができるので、開拓員は親に捨てられた子供たちです。仲間が食われているあいだに逃げろ!――そうして黒鉄の戦士となったシロは、アカという少女に出会います。
*
なんというか、今度の世界は予想外に、なかなかおもしろそうなことになってきましたが、どこから話せばいいでしょうね?
まずはこの世界の成り立ちを、少しばかり説明しておいたほうがいいかもしれません。
さて。
とあるひとつの世界に、とあるひとりの神様がいました。
神様はあるとき、不意にこんなことを思いました。
(そろそろ人間にも飽きてきたなあ、何か別の生き物を栄えさせようかなあ)
ご存知かもしれませんが、神様とは気まぐれなものです。
うろ覚えですが、たしか恐竜を滅ぼしたときもこんな感じでした。
そんなわけで神様は、とりあえず人間を滅ぼすことにして、代わりに栄えさせる別の生き物を選びました。
その生き物は、人間の大量殺りく兵器で大量虐殺されているところを、たまたま神様が目に留めて、哀れに思って選ばれたのです。
人間は、人間同士を大量殺りく兵器で虐殺することを悲しみますが、他の生き物についてはあまり躊躇なくそれを行いますよね。
神様は、人間が大量虐殺されても悲しみますし、他のどのような生き物が大量虐殺されても悲しむのです。
そこは神様と人間の、ひとつ違うところだといえるのかもしれません。
まあ、子を殺すことのできない親の気持ち、とでもいえば、神様と人間の似たところともいえるのかもしれませんが。
飽きれば滅ぼすわけですが。
ともあれ。
神様は世界を全部森にして、選んだその生き物を100倍の大きさにサイズアップしました。その生き物は、かたち的にはサッカーボールやバスケットボールを想像してもらえればわかりやすいかもしれません。
大きさを100倍にする。
たったそれだけのことで、その生き物は食物連鎖の頂点に立ちました。
いつまでもその生き物と言い続けるのもあれなので、ここからはいまの人間たちが呼んでいるように、「サイフォン」と呼ぶことにしましょう。
おやおや?
気がつかれましたか?
たしか神様は人間を滅ぼすはずじゃなかったか、と。
そう、神様は人間の街を消して、世界を全部森にして、サイフォンを食物連鎖の頂点に据えることで人間を滅ぼせると思っていたのですが――ところが人間は滅びませんでした。
案外、人間はしぶとかったのです。
文明を失った人間は、真っ先にサイフォンの餌食となって、急速にその数を減らしながらも、生き残り続けました。
サイフォンの鋭い口吻に頭を刺されて、生きながらにチューチュー脳みそを吸われる人間の姿を見て、神様はこんなことを思いました。
(……なんかやっぱかわいそうだなあ)
そこで神様は、森の中に人間の住む土地を与えたのです。
神様は森を切り開いて作ったその空間を人間の住処としました。サイフォンが森からその空間には入ってこられないようにしました。
そしてしばらくのあいだ、人間はその土地だけで繁栄していったのですが、再び増えてきた人間たちに、どうやらその土地は手狭になってしまいます。
人間たちは、いよいよ自らの手で森を切り開き、自分たちの住処を拡大しようと考えたのです。
しかし森に入った人間たちは、すぐにサイフォンの餌食となります。
18mもジャンプして、頭上から襲ってくるサイフォンに、高度な文明を失った人間は太刀打ちすることができません。
鋭い口吻で頭を刺され、脳みそをチューチュー吸われるしかありません。
ところが最近、たったひとり、サイフォンをつぎつぎと殺す人間が現れました。
それは全身が黒鉄のように真っ黒な、シロという名の人間でした。
*
さて、前置きが長くなりましたが、あちらをご覧ください。
「いやだ! いやだ! いやだ!」
「死にたくない死にたくない死にたくない死に」
いま、あちらの森の中で、人間の開拓団の一隊がサイフォンの一群に襲われています。
名目上開拓員を守るはずの兵士部隊はとっくに逃げ去ってしまい、あとに残された開拓員たちがつぎつぎとサイフォンの餌食になっていきます。
まさに混乱の坩堝です。
開拓員たちは、まだまだ幼さの残る少年少女たちです。
人口が増えすぎた森の中の人間の町には、親に捨てられた子供たちが溢れています。町の政府はそんな子供たちを保護して、必要最低限の訓練と教育を施し、開拓団として森に派遣するのです。
要するに口減らしです。
そんな子供たちの中で生き残った者が、やがては開拓団の兵士に昇格するわけなのですが、開拓員になるための教育で一番最初に教えられることは「仲間が食われているあいだに逃げろ!」ということなので、運よく兵士になったとしても、やっぱり我先にと逃げ出してしまいます。
自分の命を投げ出してでも子供たちは守る、なんて気概はこれっぽっちもありません。
勝てる見込みがあるならまだしも、普通の人間がサイフォンに勝てるなんてことはまずありえませんからね。
それも当然のことでしょう。
あ!
あれをご覧ください。
「来るな! 来るな! 来るなああああああ!」
ひとりの少年が、木を切り倒すための斧をめちゃくちゃに振り回しています。
サイフォンがどこからくるかわからないからです。
サイフォンの後脚の脚力は尋常のものではなく、体長の約60倍の高さ、100倍の距離を跳躍します。
神様の手によってサイズアップしたサイフォンの体長は、だいたい30cmほどです。
つまり高さ18m、距離にして30mを跳躍できるサイフォンが、まさにバスケットボールのように森の木々を跳ね回って移動したらどうなるか、想像することができるでしょうか?
まず人の目に捉えることは不可能です。
「うわああああああ」
おっと、そんな解説をしているうちに、さきほどの少年がサイフォンに捕まってしまいました。
地面に倒れた少年の頭には、鋭い口吻を持ったサイフォンがしっかりとひっついていますね。
まるで頭が二つになったみたいですね。
「ああああああああああああ」
なんてことを言っているうちに、サイフォンの口吻が少年の頭に突き刺さり、脳みそを吸い出し始めました。
サイフォンの好物は人間の脳みそなのです。
「あああぁぁぁぁぁぁぁぁぁ……」
少年の叫び声が、細く小さくなって、消えていきます。
一帯にはこのような光景があちらこちらに広がっています。
そして阿鼻叫喚の声がシンと静まり返ります。
どうやら、一群のサイフォンすべてが餌にありついたようです。
――と、ひとりの少女が身を起こして、仲間たちが食われている中を駆け出しました。
サイフォンには、一度食事を始めると、獲物を吸い尽くすまではしばらく動かなくなる習性があります。
仲間が食われているあいだに逃げろ!
親に捨てられた子供たちが、政府に保護され収容所に入れられて、開拓員となるべく一番最初に教わることでしたね。
少女はそれを実行します。
仲間が食われているあいだに逃げるのです。
収容所で、キャンプ地で、一緒に暮らしてきた仲間たちを見捨ててひたすら逃げます。
逃げて、逃げて、逃げて、逃げて――しかしまだ一匹、餌にありつけていないサイフォンがいたようで、向こうの木の上から少女を狙っています。
もちろん逃げるのに夢中の少女は気がついていません。
サイフォンの後脚に力が入ります。
いま、取りついていた木の幹を蹴りました。
サイフォンはコンマ数秒後には少女の頭を捕らえて、その衝撃を受けた少女は地面に倒れることでしょう、そして鋭い口吻が少女の頭に突き刺さり、少女は脳みそをチューチュー吸われてしまうことでしょう。
しかしそうはなりませんでした。
サイフォンが少女の頭に取りつこうとした瞬間、横からひとつの黒い影が現れて、サイフォンを素手で殴り飛ばしたのです。
サイフォンは近くの木に叩きつけられて絶命しました。
それはまるで一陣の黒い風のようでした。
少女が驚いて振り返ると、そこには全身黒鉄のように真っ黒な、ひとりの男が立っていました。
「お前の仲間たちは?」
男が少女に尋ねます。
少女は驚きのあまり口も利けず、ただただ自分が逃げ出してきた方向を指さします。
男は少女の指さした方向に、まるで放たれた矢のように、飛んでいきました。
*
少女が恐る恐る、惨劇の現場に戻ってみると、餌を食べていたサイフォンたちは一匹残らずそこら辺の木の幹に叩き潰され、殺されていました。
食われかけの少女の仲間たちの死体が、木々の間に点々と転がっています。
そんな中を、少女がゆっくり歩いていくと、黒い男が頭を抱えて地面にうずくまっていました。
そして、こんなことをひとり、繰り返し繰り返し呟き続けていたのです。
「なぜ逃げた、なぜ逃げた、なぜ逃げた、なぜ逃げた、なぜ逃げた、なぜ逃げた、なぜ逃げた、なぜ逃げた、なぜ逃げた、――」
「だって、そう教えられたから……」
自分のことを言われているのだと思った少女がそう答えると、男はハッと頭を上げました。
「違う! 違う! 違う! 約束したんだ! クロと! だけど僕は……」
男と少女の目が合って、男は我に返ります。
ここしばらく、ほとんど休みなくサイフォンを駆逐し続けてきたので、わずかな外的刺激にも取り乱してしまうほどに、男は疲弊していたのでした。
そう、脳を吸われた少年少女たちの死体が、辺り一面に散乱しているだけの、わずかな外的刺激にも取り乱してしまうほどに。
男は疲れていたのです。
「なぜ、こんな奥地にまできた?」
男は、今度こそ間違いなく少女に問いました。
少女の一隊は開拓団の本隊から離れて、森の奥にまで足を踏み入れていたのです。
本隊の周辺であれば、男があらかたのサイフォンを駆逐し終えていたので、ある程度の安全は確保されていますが、そこから一隊だけ離れるのはまさに自殺行為です。
「隊長が、もっと奥まで調査できれば手柄になるって」
「……そうか。生き残りはお前だけか?」
「隊長たちはすぐに逃げたからわからない。ゴートのみんなは……」
兵士以外の開拓員は「ゴート」と呼ばれています。身代わりを意味するスケープゴートの「ゴート」です。
男は黙って歩き出します。
「ま、待って! シロさん!」
少女は慌てて後を追います。
*
さて、シロと呼ばれた全身黒鉄の男と少女のいる地点は、開拓団の本隊がいたところから、人間の足で半日ほど離れています。
「開拓団の本隊が『いた』」と過去形なのは、すでに開拓団の本隊が町に引き返しているからです。
開拓団の一隊がいなくなっていることが判明すると、本隊はすぐに町へと引き返し、しかしシロだけが命令を無視して探索に残りました。
町までは、本隊のベースキャンプがあったところからもう半日かかるので、ここからは計1日の行程になります。
ベースキャンプ周辺のサイフォンは、シロによってほぼ全滅しています。辺りにはサイフォンの体液が飛び散っていて、死骸が転がっているので、ほかのサイフォンたちは警戒して近寄ってきません。
なので、まずは本隊のあった場所まで戻ることが肝要ですが、ひとつ問題があります。
もうすぐ夜がくるのです。
サイフォンは夜行性の生き物なので、夜ほど動きが活発になります。
あるいは、さきほどシロがサイフォンを駆逐した場所で夜を越せば、仲間の死骸と体液のニオイを警戒したサイフォンが、近寄ってこずに安全だったのでは、と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかしそこにはサイフォンの死骸だけではなく、開拓員の少年少女たちの、人間の死体もたくさん転がっているのです。
サイフォンたちが餌のニオイを優先したとして、なんの不思議もないのです。
だから、すみやかにその場を離れたシロの判断は、適切だったといえるでしょう。
「君の名前は?」
シロが歩きながら後ろの少女に聞きました。
「アカ」
少女が小走りに追いながら、前を行くシロに答えました。
「アカ、よく聞くんだ。もうじき夜になる。わかっていると思うが、夜になれば奴らの動きが活発になる。この辺りで野宿はできない。夜のうちもこのまま進み、何事もなく明け方までにベースキャンプ跡に辿り着ければベストだが、それは無理だろう。途中で必ず奴らの襲撃を受ける」
アカは無言で頷きました。
「僕がつぎに君の名前を呼んだら、君は近くの木の根元まで走って、木を背にして頭を抱え、できるだけ小さくなってうずくまるんだ」
「はい」
「絶対にそこを動かないこと。できるかぎり耳に神経を集中させること。そして、もう一度僕が君の名前を呼んだら、全速力で逃げろ」
仲間が食われているあいだに逃げろ!
それが、開拓員になる子供たちが収容所ではじめて学ぶことでしたね。
アカはもちろん「はい」と返事をしました。
*
夜がやってきて、森は闇に包まれています。
森の闇の中を、明かりも持たずに人間が進むのは不可能なことですが、シロにはそれが可能でした。
シロはアカの手を後ろ手に引いて進みます。
なんて冷たくて、硬い手だろう、アカは思いました。
手に触れて、少し気安くなったのでしょうか、あれ以来ずっと黙って歩き続けていたアカが、こんなことをシロに聞きます。
「シロさんは、どうしてそんなに強いんですか?」
通常の状態のシロであれば、話をするのは体力を消耗するだけなので、「黙って歩くんだ」とその質問を一蹴したことでしょう。
しかし肉体が疲労し、心も疲弊していたからでしょうか、シロはこんな昔話を始めます。
「……僕は強くなんかない」
――あるいは、自分の死のときを予感していたからなのでしょうか。
シロはだいたいつぎのような昔話をアカに語るのです。
*
むかしむかし、森の中の人間の町に、クロとシロという二人の少年がいました。
二人とも親に捨てられた孤児でした。
クロとシロは収容所で出会い、大の仲よしになりました。
収容所では「仲間が食われているあいだに逃げろ!」と真っ先に教えられましたが、クロとシロはお互いを見捨てて逃げることなんてどうしたってできないと思いました。
だから二人だけの約束を交わしました。
「もし俺たちのどちらかがサイフォンに襲われたら、俺たちだけはお互いを助けるために行動しようぜ。死ぬときは一緒に死のう」
「うん、そうしよう」
そしてはじめての開拓行動中、彼らのいる開拓団はサイフォンの群れに襲われました。
当然、兵士たちは我先に逃げ出しました。
開拓員の少年少女たちはつぎつぎとサイフォンの餌食になっていきます。
横を走っていた仲間が捕まって食われているあいだに、もう一人が必死になって逃げますが、その少年もまたサイフォンの餌食となるのです。
当時は開拓団が全滅するのも珍しいことではありませんでした。
そのほうが、人間の町の政府からすれば口減らしができて都合がよかったのです。
クロとシロも二人並んで懸命に走りました。
が、突然一人がその場に倒れ込んでしまいます。
それはクロのほうでした。
シロは立ち止まって振り返りました。
クロはうつ伏せに倒れたまま、しっかりとシロの顔を見て叫びました。
「シロ――」
そしてクロの頭にサイフォンの口吻が突き刺さったのです。
シロはどのくらいその場に立ち止まっていたのか覚えていません。
気がついたときには必死に走っていたのです。
逃げていたのです。
約束をやぶり、クロを見捨てて、しかしそんなことさえ意識せずに、逃げて、逃げて、逃げていたのです。
シロが目を覚ましたのは町の療養施設でのことでした。
このときの開拓員の生き残りはシロだけでした。
シロは、クロを見捨てて逃げたという激しい罪悪感にさいなまれます。
お互いを助けようと約束したのに。
一緒に死のうと約束したのに。
なぜ自分は逃げてしまったのか。
大の仲良しだったクロを見捨てて逃げたのか。
シロは、あのときに戻れるのなら戻りたいと、何度も何度も願います。
いまでも願い続けています。
そうすれば、今度こそクロを助けに走って、今度こそクロと一緒に死ぬことができる。
そんな思いから、その後のシロは開拓団に参加して、サイフォンの襲撃に合うたびに、できうるかぎり仲間たちを助けようと行動しました。
隣を走っている仲間が倒れれば手を貸して、まさに脳みそを吸われそうになっている仲間がいれば、伐採用の斧を手にしてサイフォンに立ち向かっていったのです。
自ら進んで死地に飛び込んでいくようになったのです。
それで救えた者もいれば、救えなかった者もいます。
もちろん救えなかった数のほうが圧倒的に多いのは言うまでもありません。
しかし、シロだけはいつも必ず生き残りました。
あの日、クロを見捨てて逃げ出したあの日以来、シロの身体にはある変化が起きていました。
まるで黒鉄のように、身体中が真っ黒に染まって、硬質化していたのです。
そして森の中を、木々を反射する銃弾ででもあるかのように、縦横無尽に跳び回るサイフォンの動きまでもが、はっきりと目に見えるようになったのです。
生き残り続けた開拓員のシロは、やがて兵士になりました。
兵士になってもシロは、仲間が食われているあいだに逃げることはありませんでした。
仲間が食われているあいだに逃げることをしませんでした。
できませんでした。
それはまるで、クロに対する贖罪のように。
いまもあのときに戻ることを願い、逃げることを拒み、一番危険な場所に立って、シロは戦い続けているのです。
*
真っ暗闇の森の中で、真っ黒な戦士シロが、銃弾のごとく跳び交うサイフォンを相手に戦っています。
殴っても殴っても殴っても殴っても。
蹴っても蹴っても蹴っても蹴っても。
潰しても潰しても潰しても潰しても。
サイフォンはつぎからつぎへとシロをめがけて跳んできます。
開拓団が町を発ってからずっと、シロは休みなく戦い続けてきました。
アカの所属する一隊が本隊からいなくなったとわかってからは、ほとんど駆け続けにその跡を追ってきたのです。
さすがに疲労も限界に達しようとしていました。
一本の木の根元でうずくまるアカをかばいながら戦わなければならないことも、シロの消耗を早める一因となっていました。
極限状態にありながらも、シロは不思議な安らぎを感じていました。
身体は勝手にサイフォンを殴り、蹴り、潰しながら、頭はまったく戦いから離れていたのです。
ああ、これでようやく楽になれるのか。
神様。
僕はクロとの約束をやぶりました。
僕はクロを見殺しにしました。
僕の身体が真っ黒になったのも、きっとそのせいだと思います。
だけど僕は、クロを見捨てたあの日から、あらゆる危険と戦ってきました。
それはひとつには、この黒い身体をみると、クロを見捨てて逃げた自分を恥じる気持ちが湧き起こってきたからです。
だけどそれにはもうひとつの理由があります。
僕はこの黒い僕を殺したさに、あるいは倒れ伏した仲間の手を取り、あるいは死に直面した仲間を助けに、死地に飛び込んでいったのです。
だけど不思議と、どんな死地にあっても、僕の命が奪われることはありませんでした。
そんな僕の命もどうやらここで終わりのようです。
ああ、これでやっとクロに会える。
クロに謝ることができる。
たとえ許してもらえなくてもいい。
どれだけ罵倒され、殴られたってかまわない。
神様、どうかお願いします。
もう一度クロに会わせてください。
クロに謝る機会を僕に与えてください。
そこでシロの意識はふと現実に戻ってきます。
そうだ、こんな思いをあの少女に、アカにさせてはいけない!
そのとき、シロは後頭部に強い衝撃を受けてうつ伏せに倒れてしまいます。
ついに一匹のサイフォンが、シロの頭部を捕らえたのです。
シロは最後の力を振り絞って顎を強く上げました。
そして口を大きく開きました。
「アカ――」
逃げろ!
そう言い放った瞬間、シロの脳裏にあの日の光景がよみがえりました。
そうです。
クロを見捨てて逃げたあの日のことです。
クロは、たしかにシロの顔を見て、こう叫んだのです。
「シロ逃げろ!」
それは本当に現実にあったことなのでしょうか?
ショックのあまりシロが封印していた記憶なのでしょうか?
あるいは自分の心を慰めるために、シロが作り出しただけの、ただの都合のいい幻だったかもしれません。
だけどシロにとって、そんなことはどうでもよかったのです。
もしあのとき、クロと自分の立場が反対だったなら、サイフォンに捕まったのが自分で、立ち止まって振り返ったのがクロだったのだとしたら――
クロ逃げろ!
シロは迷いなくそう言ったはずです。
そのことを確信できたから、シロは最後に救われた気持ちになることができたのです。
ですが――
「うわああああああああああああ!」
真っ暗闇の森の中で、常人離れしたシロの目が捉えたのは、障害物となる木々も気にせず、むちゃくちゃに斧を振り回しながら、シロの声がしたほうに、がむしゃらに走ってくるアカの姿でした。
シロは思います。
ああ、僕は勝手に思い込んでいた。
あの少女が罪を背負って生きなくてもいいように、なんて、とんでもない思い違いをしていた。
あの子は僕よりもはるかに強い。
だからあの子を死なせてはならない!
いままさに、木の幹を蹴った一匹のサイフォンが、アカに向かって跳びかかっていきます。シロの目は、その状況をまるでスローモーション映像を見るように、克明に捉えています。
シロは渾身の力を込めて立ち上がると、自分の頭に取りついているサイフォンを両手で掴み、そのままアカを狙っているサイフォンへと投げつけました。
投げ飛ばされたサイフォンと、跳んできたサイフォンは宙で互いにぶつかり合って潰れました。
*
木漏れ日が森の中を薄明るく照らし出します。
一本の木の根元に少女を抱いた黒い男がしゃがみ込んでいます。
あたりの木々には潰れたサイフォンの死骸がべっとりとはりついて、土の上には無数のサイフォンの死骸が転がっています。
朝になれば、夜行性のサイフォンは活動をやめ、これだけ周囲にサイフォンの死のニオイが満ちていれば、警戒してそうやすやすとは近づいてこないでしょう。
戦いは終わったのです。
シロはアカを守り切ったのです。
満身創痍のシロは、口を開くのもつらかったはずですが、これだけは聞いておかねばならないと思いました。
「なぜ、逃げなかった?」
アカは温かな黒鉄の胸からゆっくりと顔を上げて、シロの顔を見て言いました。
「あなたはまだ死んではいけない人だと思ったから」
*
さて、冒頭でも述べましたように、神様とは気まぐれなものです。
そろそろ眠くなってきたので、今回のお話はこのあたりで終わりたいのです。
え?
中途半端ですって?
そんなの知りません。
そんなの無責任だ?
やれやれ。
しょうがないですね。
ならばシロの物語を端的に最後までお話しましょう。
それからシロとアカは昼頃までそこで休み、携帯食料を食べて、体力を回復させると再び歩き出してベースキャンプまで辿り着きます。
そこには3m級のマントーディアがいて、首をひとつカマで切り飛ばします。
ちなみにマントーディアは、いま神様が即興で創造しました。
神様は、なかなかそんなことはしないのですが、たまには人間のお願いを聞いてあげたくなっちゃうんですよね。
はい、これでこの物語はおしまいです。
え?
首はひとつしか飛んでいない?
どっちの首が飛んだのか?
そんなことは想像してみればわかるでしょうに。
生き残りがいるなら物語には続きがあるはずだ?
そうですね。
また気が向いたらお話することもあるかもしれません。
だけどとにかくいまは眠くて眠くてしょうがないのです。
だから今回はこれにておしまい。
それではおやすみなさい。
<SHIRO is END. To be continued in AKA…..?>
※
読んでいただきありがとうございました。
※オリジナル小説は、【狐人小説】へ。
※日々のつれづれは、【狐人日記】へ。
※ネット小説雑学等、【狐人雑学】へ。
※おすすめの小説の、【読書感想】へ。
※4択クイズ回答は、【4択回答】へ。
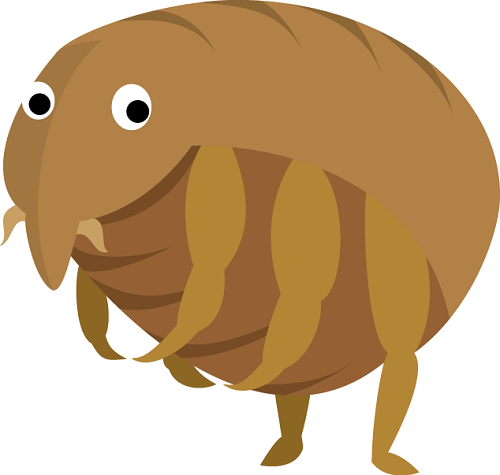

コメント