読書時間:およそ10分。
あらすじ:20XX年。総理大臣に替わり、カミサマが治めるこの国でのこと。例えば、消費税率は50%。でも、文句を言う人は少ない。なぜなら、全国民に月々20万デジタル円が支給されるから。労働のAI化・機械化。最近流行りのVRゲーム。そんな現代の朝。私が目を覚ますと、そこには二人の小人がいて――
1
朝、目を覚ますと。枕の上にさらに腕を枕にして。横向きに寝ている私の顔の前にやっぱり二人の小人がいて。これはまだ昨夜の悪夢の続きを見ているのだろうか……。寝起きの頭で考えてみてもその可能性は低そう。これほどはっきりとした知覚が悪夢であるならば、もはや悪夢と現実を区別することに如何ほどの意味があるだろうか。みたいな胡人の悪夢。
二人の小人は、「まさにこれぞ」と強調すべき見事な団子鼻の下に、黒い大きな口髭を生やしている。共に中年男性のように見えるけど、色艶はよくて、じつは意外と若かったりするのだろうか。一人は小太りで、一人は瘦せていて。兄弟みたいに似てて。どういうわけか、就寝中の主人を一晩中傍らで見守る家臣が如く、仲良く並んで正座をしていた、全裸で。
「……」
「……」「……」
目覚めの一杯ならぬ目覚めの一景に、おしるこ缶ならぬ中年男性の裸はきっついな。と、思ってしまうのは私だけ? 股の間から亀さんの頭がコンニチハしているよ。ダブルで。
地獄村の武者だってパンツくらいはいてるぞ。夢なら覚めてよ。とムダに現実逃避をしてみたところで、ピピピピッピピピピッ――、枕元に置いた端末からアラームが鳴った。これで視覚のみならず聴覚によってもこの現実が夢である可能性は否定されたわけだ。
「おはようございます」
まるでアラームが鳴るのを待っていたかのようなタイミングで小太りの方の小人が朝の挨拶を述べた。
「……おはようございます」
仕方なく私はこの現実を受け入れ、二人の小人に儀礼的に朝の挨拶を返してから、端末の画面をドラッグ。アラームを解除。起き上がると布団を畳み端に寄せ、大学へ向かうための準備に取り掛かることにした。
トイレで用を足して、歯を磨く間に私は昨夜の夢のような出来事について思い返してみる。それは深夜、ふと目が覚める、といったよくあるパターン。しかし、何かの気配を感じて、となれば年に数回程度のレアケース。
確か前回は、暗い部屋の天井の一点に、黒い小さな影を捉えた。継続して睡魔が襲う中、端末に手を伸ばしてドラッグからのタップ。慣れた操作で照明をつければ、そこに張りつく黒い小さな影の正体はGであった。寝惚けた頭で選択肢を選択。処理するか・無視するかの二択。Gジェットを両手に構え、いざ不法に占拠された我が部屋の天井をレコンギスタすべく迷ったものの。結局は睡魔に抗しきれず、重い瞼をそっと閉ざしたのだったか。
『くっ! 逃がしたかっ!』『縦合体なら届くのでは?』『よし! では縦合体だ!』
そして今回、そんな会話を耳にした気がしての一時覚醒と相成り。今にして思えば、縦合体って何だ。双子蜂か。――ツッコミを入れざるを得ない。岬の灯台を視界の端に映しながら、真っ青な海の上を飛翔するが如く。襲来する包丁やお皿の群れを両手で弾を投げて迎撃するこの感じ。白い雲の中から飛び出した黄色のベルは、赤色に育てて取りたい心意気。
しかし、その瞬間はといえば……。寝不足の朦朧とした頭でそこまで考えるには至らず。寝惚け眼で照明をつけて。薄く開いた目線の先に。捉えたのはスーパーアンコブラザーズ。兄のアンコと弟のキナーコが。なぜか我が部屋のフローリングで肩車をしていたのだ。全裸で。
なぜ太った兄が上で、瘦せた弟が下なのか。これが主役と脇役の差か。もちろん先と同様、そんな指摘を挟む余裕はなくて。
『……』『……』
『……』
兄弟と私はバッチリ目を合わせたまま。互いに見つめ合うことしばらく。
『不法侵入……詳しい話……明日、聞きますので……』
私はどうにかそれだけを伝えて、深い眠りの底に再び落ちていったのだった。
バス・トイレ一緒の浴室から出て、視線を向ければやっぱりそこには二人の小人がいる。こちらに向き直って正座をしている。どうして私は昨夜のうちに「出て行ってください」と退去を勧告しなかったのだろう。――とか、後悔しても後の祭りか。
「じつは我々、施設を抜け出してきまして」
やにわに。例によって小太りの方が語り始めた。私は冷蔵庫からミネラルウォーターのペットボトルを取り出し、台所の水切り棚からグラスを取って水を注ぎ、それを飲みながら小人の言葉に耳を傾けた。
施設というのは何かの実験施設らしい。そこで小人は大量生産され、日夜いろいろな実験が行われているのだという。
「我々はそのような境遇に耐えかね、小人の基本的人権の保障をお願いすべく、カミサマを探しているところなのです」
その途上でこの部屋に辿り着いたという。私はジーンズをはいて、Tシャツを着た。
「そこでしばしの拠点として、こちらに住まわせては頂けないでしょうか」
アンコとキナーコが同時に額を床につけた。これが世にいう裸土下座というやつなのか。中年男性の裸土下座とは一体誰得なのだろう。――そんな疑問はさておき。確かに、この国にカミサマはいる。しかし、その正体を知る者は誰もいない。ならば、その探求に長期戦で臨むのは自明の理。そのための拠点確保もまた然り。けれど、それがよりによって私の部屋って。ルームシェアって。……うち六畳一間なんですけど。
とりあえず私は鞄を掴んだ。これから大学へ行かなければならない。高等教育といえば趣味みたいなものだが、さりとてお金を支払っているんだから、休んだりしてはもったいない。
「では、家賃を三分の一ずつシェアしましょう。私はこれから大学へ行ってきます。続きはまた帰ってから話をしましょう」
「……」「……」
裸一貫たる小人達に、私はそう言い置いて部屋を出た。
これが今朝の話である。
2
大学の帰りにスーパーに寄って。ひき肉の大容量パック、玉ねぎ一袋、トマト一パック、冷凍ブロッコリー一袋、赤パプリカ一個、黄パプリカ一個、キャベツ一玉、レタス一玉、牛乳一パックをエコバッグに入れて店を出る。――と、すぐに端末に通知が来て。内容を確認すれば、今の買い物の領収証だ。合計2741円、うち消費税913円。税率は当然50%也。
消費税といえば8%という時代もあったらしく、今と比べて五分の一以下の税率ならばさぞかし暮らしやすかったのかと思えば、そんなこともなかったのだとか。AIや機械が未発達だった頃は、現代よりも職業選択の幅が広かったとはいえ。ならば高収入の職に就きやすく、多くの国民が豊かな生活を送れたように錯覚するのだけれど、実際には格差が大きく、半分くらいの人達はワーキングプアともいわれていた。それは偏に、BIがなかったから。現在では、全国民に生まれてから死ぬまで月々20万デジタル円が支給される仕組みがあるが、当時はこれがなかった。労働のAI化・機械化が進んで職業選択の幅は狭くなったものの、この所得補償があるために国民は一生涯働かなくても最低限生きていけるのが昨今の世相である。月20万円の支給ということは年240万円。これを少ないと言う人もいるけれど、働かずにそれだけ貰えれば御の字、というのが私の所感だ。かつては国民の多くが働いて、そのくらいの所得を得て生計を立てていた過去を鑑みるに、現在はとても幸せな時代だといえるのではなかろうか。誰だって労働をせずに生きられるならそれに越したことはないだろうし。海外旅行などの派手な遊びは難しくとも、それに代わる安価な娯楽は今の時代たくさんあるわけで。例えば、近年のトレンドはVRゲーム。それぞれがそれぞれの世界に没入し、俺TUEEEするもよし、悪役令嬢するもよし、領地経営するもよし、成り上がるもよし、ざまぁするもよし、ハーレムするもよし――思いのまま。肉体の管理を機械に任せ、長期的にVRゲームをプレイできる施設が大ブームとなっている。ちなみに私はピコピコやるレトロゲーム愛好家なのでVRゲームは未経験。けれど、一度手を出せば抜けられなくなるだろう危機感は抱いていて、なかなかダイブに踏み切れない、というのが正直なところ。――そんなこんな取り留めのない思考を巡らせつつ家路についた。
「おかえりなさい」
玄関ドアを開けると、二人の小人が上がり框のところに正座をして、私を迎えた。今朝と変わらぬ姿である。つまり、全裸の中年男性×2=亀さんコンバンハダブルである。
「……ただいま」
部屋に入って、買ってきた食材を冷蔵庫にしまいながら私は、「おかえり」を言われたのも「ただいま」を言ったのもいつぶりだろうかと考えた。
私の家はシングルマザーで、母は女手一つで私を育ててくれたということになるが、育ててくれたとはいっても、お金を出してくれたくらいにしか私は認識できていなかった。もちろん、義務教育を終えるまではBIによる支給金を勝手に使うことができないため、親がお金を出してくれるということはそれだけでありがたいには違いない。けれども、お金だけ出して「これで好きなものを食べなさい」と言われても、なんだか味気ない気がしていた。母はほとんど家にいなかった。何をしていたのかも知らない。「親も一人の人間であり、たとえ子供を得たとしても、自由に人生を謳歌する権利がある」といったようなことは義務教育で学んでいた。だけど、もう少しくらい構ってくれないかな。たまには一緒にご飯を食べてくれないかな――こんなふうに考えてしまう子供は確かに罰当たりなのかもしれないけれど。そんな気持ちは、小学校の時にはただ寂しく、中学校に上がれば反感に、高校では諦念に変わって。今では、そういうものかと大した感慨もなくなってしまったな。
「はぁ!」「とぉ!」
狭い台所で夕飯の支度をしていると、室内で跳ね回る小人達の様子が目に入ってきた。凄いジャンプ力だ。
「……何をしているんですか?」
「じつは家賃を支払うためにTuberになろうと思いまして。その練習を」
Tuberといえば、動画を作って配信して、それで広告収入を得るあのTuberのことか。
「小人が飛び跳ねているだけで、これがなかなかウケるのではないかと」
確かに、この世に小人が存在するなど初耳だった。それだけで、注目を集めるには過ぎたる事実であるかもしれない。そこにアクティビティを加えたらどうだ。ティーカップのお風呂で入浴したり、スーパーアンコブラザーズの舞台を再現して冒険してみたり、あるいはペットボトルロケットに乗って空を飛んでみたり――企画の可能性は無限大にも思えてくる。Tuberは今の時代も、漫画家や小説家、ゲームクリエイターなどに次いで人気の職業となっている。外科手術をフルオートでこなせるAIも、面白い漫画や小説、ゲームなどを創造する域には未だ至っていない。
白いまな板の上でキャベツを千切りに、赤と黄のパプリカを細切りに、トマトを適当に切って、レタスを手でちぎり、冷凍ブロッコリーをそのままに、大きなボウルに入れてラップ、冷蔵庫へ。ひき肉と玉ねぎはハンバーグのタネにして、ラップに包んで小分けにし、冷凍庫にしまった。
それからサラダとハンバーグを一人分ずつ用意、冷凍ご飯を電子レンジでチンしようとしたところで、ふと気づいた。
「お二人もご飯食べますか?」
私は小人二人に一応尋ねてみた。
「今すぐお支払いできるお金はないのですが」
それはわかってる。
「出世払いで頂けますか?」
「構いませんよ」
Tuberにも出世はあるんだろうか。
ハンバーグとサラダとご飯一人前(小人二人分)でいくらくらいになるか計算しながら、夕飯の準備を進めた。
お皿に盛りつけたハンバーグとサラダ、保存容器のまま出したご飯をちゃぶ台の上に並べたところで、さて、箸やフォークやナイフといった食器はどうしたらいいのかと疑問を抱く。生憎、小人専用の食器はうちにはない。
「美味しいですなぁ」
しかし、そんな配慮は不要だった様子。小人達は両手でハンバーグやご飯をちぎっては豪快にかぶりついて食事をしている。そんな光景を眺めながら、ふとある思いが過る。一緒にご飯を食べてほしい――私は母に訴えたことがあっただろうか。母は私がそう言いさえすれば、一緒に食事をしてくれたのではないか。こうして私が食事を準備し、一緒にご飯を食べようと言いさえすれば。
それにしても全裸で全身を使って豪快に食べる中年男性二人の姿を眺めながらする食事って……。
こうして誰も知らない私の平凡な今日という日は過ぎていった。
※
読んでいただきありがとうございました。
※オリジナル小説は、【狐人小説】へ。
※日々のつれづれは、【狐人日記】へ。
※ネット小説雑学等、【狐人雑学】へ。
※おすすめの小説の、【読書感想】へ。
※4択クイズ回答は、【4択回答】へ。
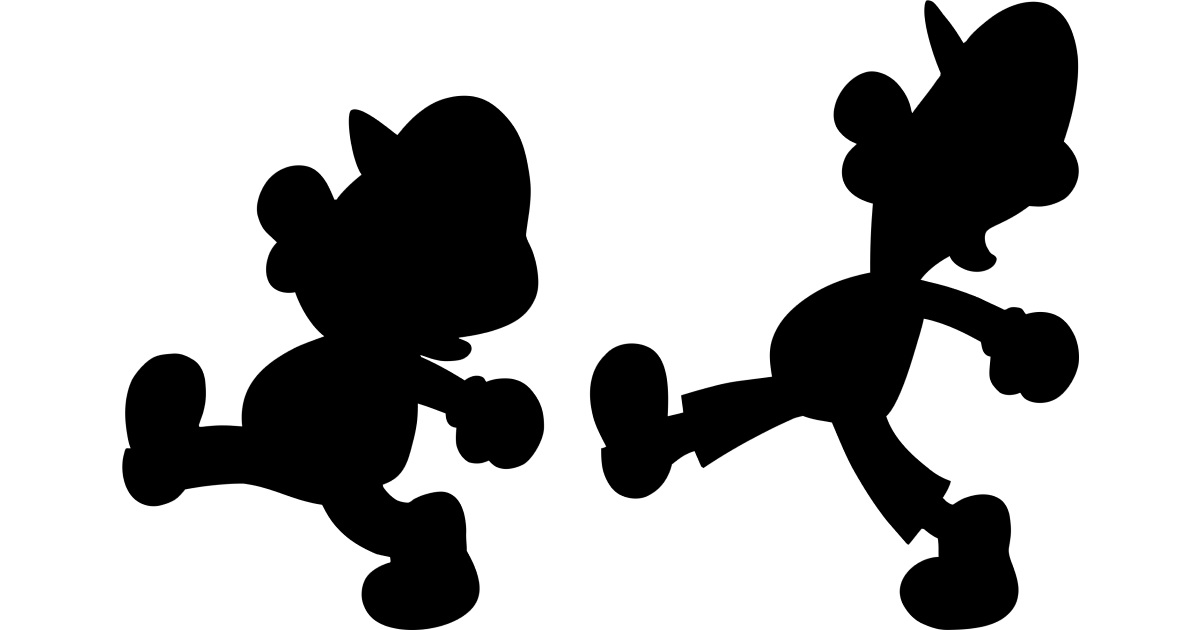


コメント