狐人的あいさつ
コンにちは。狐人 七十四夏木です。
読書していて、
「ちょっと気になったこと」
ありませんか?
そんな感じの狐人的な読書メモと感想を綴ります。
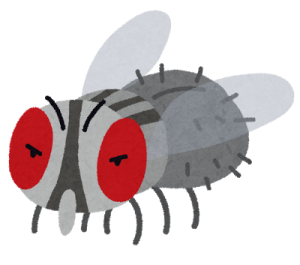
今回は『冬の蠅/梶井基次郎』です。
文字数11000字ほどの短編小説。
狐人的読書時間は約53分。
梶井基次郎の最高傑作との呼び声高い。
近代日本文学の名作。運命と才能の小説。
重病人の気持ち。励ますのは残酷?
延命治療と副作用。
蜘蛛は小さな天女! 冬の蠅は元気ない。
みんなは元気?
未読の方はこの機会にぜひご一読ください。
狐人的あらすじ
序
冬の蠅とは何か? 夏の元気を失った冬の蠅。そんな彼らから着想を得て書かれた、これはそんな一編の小説である。
1
溪間にある温泉宿で、病気療養中の「私」は、冬になると日光浴をはじめた。そうしていて気がついたのは、冬は日蔭でよぼよぼしている蠅が、日なたの中では生き生きとしている事実だった。「私」はそこに「生きんとする意思」を感じた。
「私」は太陽を憎んだ。日光の熱は血行をよくしてくれるし、ほかほかと心を楽しませてくれるが、日光浴の時間が過ぎ去ってしまえば、また病気の苦痛が「私」を襲う。それは太陽が「私」を生かしてくれようとしているようで、じつは生かす気などさらさらないというふうに感じられて、騙されているような気がして不快だった。
夜になって寝床へ入ると、天井にじっとはりついている蠅が見える。「私」は「私」の病魔が、ほかの部屋には棲んでいない冬の蠅を、「私」の部屋に棲まわせているのではないかと考える。いつになったらこうしたことにけりがつくのか。「私」は不眠を紛らわせるために、自分の生命を絶つあらゆる残虐な方法を空想した。冬の蠅がじっとはりついている一室で。
2
よく晴れた温かい日に、「私」は村の郵便局へ手紙を出しに行った。その帰り、疲れた「私」は乗合自動車に乗ったのだが、それは「私」の滞在している宿とは別のところへ向かう車だった。
日も暮れて、「私」は山の中で車を降りた。それはあまりに疲れたために、もう自分自身を山中に遺棄してしまいたい、と無意識のうちに願ってしまったからかもしれない。「私」は力尽きるまで歩き通すつもりで山の中を歩き続けた。
夜遅く、「私」は半島の南端の港に立っていた。途中とある温泉宿に辿り着き、温泉につかって食事をしたが、また歩き出してこの港町に辿り着いたのだった。「私」はそこで三日ほどを過ごしたが、冬の蠅のいるあの部屋が、自分の身にしみついてしまっていることを知って、もとの温泉宿に帰った。
3
帰ってきた「私」は何日も寝たきりの状態になった。そんなある日、自分の部屋に蠅が一匹もいなくなっている事実に、ふと気づく。おそらく「私」の留守の間に、「私」の部屋に日を入れなかったからに違いない。「私」の日光浴は、冬の蠅にとって生存の条件だったのだ。そして「私」にも、そんな気まぐれな生存の条件があるような気がした。それは「私」の自尊心を傷つける新たな空想だった。そしてその空想が、「私」の生活をますます陰鬱にしていくのを感じた。
狐人的読書感想

『冬の蠅』は「梶井基次郎の最高傑作」に挙げる人も多い作品だそうで、僕もその意見には頷かされるところがあります。
すごい小説だといってしまっていいと思いました(梶井基次郎作品でこれを言うのは何度目になるかしれませんが)。
この作品の大きなテーマとして「気まぐれな生存の条件」、つまり生物の「生」というものは、人智の及ばない運命的な何かに支配されている、というようなことが描かれているかと思うのですが、このあたりは中島敦さんの作品にも通じるところがあるような気がしました。
梶井基次郎さんと中島敦さんといえば、おふたりとも呼吸器系の病気(梶井基次郎さんは肺結核、中島敦さんは気管支喘息)で若くしてお亡くなりになっています(梶井基次郎さんは31歳、中島敦さんは33歳)
狐人的にはこのおふたりの作品は、もっと読んでみたかったなあ、と思わされることが多く、なので早逝が惜しまれる作家さんである、というところも共通しています。
命にかかわる病というものが、「生」と「すぐ目の前にある生の終わり」というものに、深く目を向けるきっかけになる、というのはわかるような気がします。
わかるような気がするのですが、だからといって病気のひと全員が全員、こうしたすばらしい小説が書けるわけではありませんよね(つまり僕には病気になっても書ける自信がないということ)。
それを優れた小説に仕上げるというのは、やはり文学的才能があってこそだと感じられます。
鋭敏な感覚と文学的才能があって、だからこそ、この作品を世に生み出すために、人智の及ばない何かによって、こうした作家さんたちが病気を患ってしまったのではなかろうか、などと想像すると、そこにもひとつ運命的なものを(勝手に)感じてしまい、より趣深くこれらの作品を楽しめるように思いました(またしても当たり前のことを言っているかもしれませんが)。
病気のためというのはもちろんあるのでしょうが、僕だったら冬の蠅を見ていてこういったことを考えることはないんじゃないかなあ、と思いました。
その点、梶井基次郎さんの観察眼というか、感覚の鋭さというか、ものごとの捉え方というのは本当にすごいと実感します。
「私」が太陽を憎んだという件は、とくに命にかかわる病気のない僕でも、わかるように思います(夏の暑い、太陽が憎い、という意味じゃなくて)
日光の熱が血行をよくして一時的に苦痛を緩和してくれるけれど、太陽が沈んでしまえば再びあの苦痛が襲ってきます。そんなことを日々繰り返していれば、太陽を憎いと思う気持ちも、どこか当たり前のことのように感じてしまいます。
……ふと思ったのですが、このことは、やはり人生そのものを表しているようですよね。
人生も、いつも楽しいことばかりではありませんし、つらいことや悲しいことだってあります。ときに「もう生きているのがいや」になることだってあって、人生を憎む気持ちになることだってあって、これはやっぱり太陽を憎いと思う気持ちと、通じているように思うのです。
あるいは恋人との別れみたいなことも連想しました。楽しかったはずの思い出も、結果的には思い出すと苦しくなってしまうような思い出になる、みたいな。まあこの場合、失恋の痛手は時間経過により忘れることができるかもしれませんが、命にかかわる病気というのは時間経過とともに苦しくなる一方だ、というところに明確な違いがあるでしょうね。
現代でも、たとえば癌の薬物療法や放射線治療は、根治治療というよりも延命療法の趣が強いように思います。これらの副作用というのは相当に苦しいものだと聞きます。
そうすると、それを受ける患者さんの、こういった治療に対する思いというのは、『冬の蠅』でいうところの「私」の太陽を憎む気持ちと通じるものなのではないでしょうか?
「いっそはやく楽にしてくれ」などと言われてしまうと、「がんばって病気と闘いましょう!」などと励ましたい気持ちになってしまいますが、軽々にそんなことをいうのも残酷なような思いがしました。
重病のひとには、がんばって病気と闘ってほしい、と僕などは勝手に望んでしまいがちになりますが、本人からしたらそんな言葉は拷問と変わらないものなのかもしれません。
『冬の蠅』の「私」のように、終始鬱々とした気持ちになってしまうのはわかる気がします。
だけどそれだけに、病気と闘って前向きに生きているひとたちというのは本当にすごいな、ということを思いました。
テレビなどを見ていて漠然とそのことを思う機会は少なくないようにも感じるのですが、ここまでの実感を持って思ったことはなかったような気がするのです。
もしも僕の周りで命にかかわるような病気になってしまったひとがいるとき、その接し方についてきちんと考えなければならないし、また自分が重病にかかってしまったとき、ただ自暴自棄になるのではなくて、周囲のひとたちを明るくできるほどに前向きに生きることができるだろうか、とそんなことを考えた読書でした。
もちろん、言うは易く行うは難し、なのですが……。
読書感想まとめ

命にかかわる病気にかかってしまったひとの気持ち。
狐人的読書メモ
夏の蠅はうっとうしいほど元気だけれど、冬の蠅は元気ない。普段うっとうしいのに元気ない。それはちょっとだけ寂しいことのようにも思いました。(蜘蛛が)小さな天女! という描写がなんか好き。
・『冬の蠅/梶井基次郎』の概要
1928年(昭和3年)『創作月刊』(5月号)にて初出。「梶井基次郎の最高傑作」との呼び声も高い。近代日本文学の名作。が、発表当時は批評さえされていないような作品だったらしい。作品集『檸檬』収録、刊行後に注目されるようになる。
以上、『冬の蠅/梶井基次郎』の狐人的な読書メモと感想でした。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
(▼こちらもぜひぜひお願いします!▼)
【140字の小説クイズ!元ネタのタイトルな~んだ?】
※オリジナル小説は、【狐人小説】へ。
※日々のつれづれは、【狐人日記】へ。
※ネット小説雑学等、【狐人雑学】へ。
※おすすめの小説の、【読書感想】へ。
※4択クイズ回答は、【4択回答】へ。


コメント