読書時間:およそ10分。
あらすじ:フェチとかSとかMだとか、ちょっと読んだだけで、あたしのご主人様のこと、ヘンタイだ!って思うかも。だけど、誰にだって、ひとには言いにくいこと、あるんじゃない? 最後にはみんなにわかってもらえるって信じてる。
*
そうだ。カミングアウトしよう。
と、私は思う。
それは、とても恥ずかしいことのような気がする。
しかし秘密の一つや二つ、誰にだってあるだろう?
そして、それが変態性癖のように思われてしまう。
そんなものも少なくないのではなかろうか?
たとえばフェティシズムというものがある。
胸フェチ、尻フェチ、足フェチ。
あるいは。
筋肉フェチ、鎖骨フェチ。
などなど。
この世にはじつにさまざまなフェチがある。
しかしこれらのフェチは、厳密には変態性癖とはいえないものだ。
これは、
『誰にだって好きな身体のパーツくらいあるものだから』
という所見で納得してもらえると思う。
真の変態性癖とは。
たとえば動物性愛(獣姦、ズーフィリア)のようなものをいう。
では、SMは変態性癖か?
私はSMもフェチと同様に理解している。
「はじめまして。あたし、ドSだから。よろしくね」
「ぼくはドMです。よかったら仲よくしてください」
……まあ、おおっぴらに話されることはあまりないかもしれないが。
とはいえ、人間、
「あなたはSですか、それともMですか」
と問われれば、
「どちらかといえばSですね」
「どちらかといえばMよ」
というふうに答えられるはずだ。
むしろ臆面もなく、
「自分はN(ノーマル)だ」
なんて言う人間を、私は信用しない。
とかなんとか。
つまり。
私が何を言いたいのかといえば。
私がこれからするカミングアウトとは、まさに以上のようなことなのだ。
つまり。
引かないでほしい。
と、いうことなのだ!
『……なら、わざわざカミングアウトなんかしなくてもいいんじゃない?』
と思われる紳士もいることだろう。
『そんな秘密は墓場まで持っていけ』
と、思われる淑女もいるかもしれない。
しかし、どうかそんなことは言わないでほしい。
人には言いにくい趣味、だけど誰かと共有したいこの気持ち。
というものが、たしかにあるだろう?
マニア、オタク、腐女子、腐男子――
諸君には私の気持ちが理解できるのではなかろうか?
そう。
私が言いたいのも「この気持ち」ということなのだ。
私は声を大にして言いたい。
私はカミングアウトする。
「私は彼女を愛している」
と。だから、
「私は彼女を愛撫する」
と。
ただしそれは、性的な意味合いにおいて、ということでは決してない。
表面上のことはどうあれ、私が真実言いたいのはそれなのだ。
ということを、まずは覚えておいてもらいたい。
そして最後には。
きっと多くの諸氏に共感してもらえるだろう。
と、私はそのように信じている。
*
まずは彼女の耳の話だ。
彼女の耳というのは本当に不思議ものだ。
薄くって、冷たくって。
タケノコの皮のよう。
表にはやわらかな毛が生えていて、裏はピカピカしている。
触感は硬いような、やわらかいような。
彼女の耳は特別な物質だ。
私は子供のころから、じつはある欲望を、彼女の耳に対し抱いていた。
一度、彼女の耳を、穴あけパンチで「パチン!」
とやってみたくてたまらなかったのだ。
これははたして残酷な空想だろうか?
私は「否!」と答えたい。
なぜならそれは。
彼女の耳に宿る一つの不思議な示唆力によるものだから。
私にはそう思えてならないからだ。
彼女の耳に惹かれるのは何も私だけではない。
実際、子供も大人もみんな、彼女の耳を触りたがる。
そして子供の無邪気な空想というものは、じつは案外執念深かったりする。
パンチで「パチン!」とやるような空想も然り。
それは思い切って行動に移さないかぎり。
我々のアンニュイの中に、はるかに長く生き延びる。
すでに充分な常識を身につけた大人の私。その私が。
いまだ熱心に「パチン!」のことを考えてしまう。
これには自分でも驚いてしまうやら呆れてしまうやら……。
ところが。
最近、ふとしたことから。
この空想の致命的な誤算が判明してしまった。
それは――
彼女も耳を痛がる。
という厳然たる事実だった。
そもそも、耳は元来痛みを感じにくい部位だ。
それはピアスをあける人がいることからもわかるだろう。
耳をある程度強い力でひっぱっても。指でつまんでみても。
彼女はいたって平気だった。
『ふふふ。なあに? くすぐったいわ』
そんなことを言わんばかりの様子であった。
だから――と言うのも言い訳がましく聞こえてしまうかもしれないが。
だが、私は彼女の耳に不死身のような疑いを抱いてしまっていたのだ。
そしてある日。
私は彼女とのプレイの最中。とうとうその耳を噛んでしまった。
それは私にとって発見ともいうべき出来事だった。
私に耳を噛まれた瞬間、彼女はたちまち悲鳴を上げた。
まさに、
『痛い!』
というのが、ダイレクトに伝わってくる悲鳴だった。
私が子供のころから持ち続けていた空想は。
その場で粉々に砕けてしまった。
彼女は、耳を噛まれるのが、一番痛いのだ。
彼女は怒ったように私から身を離した。
それで私は自分のしたことを後悔した。
私は反省し、彼女に謝り、二度とこのようなことはしないと誓った。
こうして私の子供のころからの空想は消えてしまった。
ある日、仲よしの異常に美しい少年。
彼が私の前を走っていて、すうっと。
まるで空中に吸い込まれる冬の日の白い吐息のように。
忽然と姿を消してしまったみたいに。
しかしながら、人間というのは懲りない生き物である。
というか、こういうことには際限がないみたいである。
私はまた新たな空想にとりつかれてしまうのだ。
*
つぎは彼女の爪の話をしよう。
私が新たにとりつかれた空想とは。
彼女ご自慢のネイルを全部切ってしまったら……
彼女はいったいどうなってしまうのだろう?
ということだった。
おそらく彼女は死んでしまうのではないか?
いつもきれいに手入れをしている爪が突然なくなってしまうのだ。
たとえば。
爪で缶コーヒーのプルタブを開けようとして――できない!
さりげなく人にネイルを見せようとして――笑われてる?
爪を研ごうとして――そんな爪はない!
彼女はこんなことを何度も何度も繰り返すうちに気づくだろう。
今の自分が昔の自分とまったく違うということに。
そしてだんだんと自信を失っていく。
もはや自分がその「高さ」にいることにさえ。
彼女はふるえるようになる。
その高さから「転落」する――そのことからいつも自分を守ってくれた。
彼女の自信の象徴だったネイルが、もはやないのだから。
自信に満ち溢れていた彼女が。輝いていたあの彼女が。
よたよたと歩く別の動物になってしまうのだ。
ついにはよたよたと歩くことさえしなくなってしまう。
ああ! なんという絶望!
私はきっと、かいがいしく彼女の世話をすることだろう。
彼女が誰からも見向きもされなくなったとしても。
私だけは彼女を愛し続けるだろう。
だが私のそんなかいがいしさもむなしく。
彼女は絶え間ない孤独な夢を見ながら。
いよいよ食べる元気さえ失くしてしまう。
そして死んでしまうのだ。
ああ、爪のない彼女。
こんなに頼りなく、哀れな存在がほかにあるだろうか?
それは声が出なくなったアーティスト。
若年性アルツハイマーになった天才児にも似ている。
こんなことを考えるとき。私はいつも。今すぐにでも。
彼女を抱きしめてやりたい衝動に駆られるのだ。
このような空想はいつも私を悲しくさせる。
その比類なき悲しみは。
爪を失って生きていくくらいなら死んでしまったほうが彼女の幸せのため。
そのためにはよかったのではなかろうか。
などと、普段なら考えそうにもないことさえ、平気で受け入れそうになる。
いや、その結末の妥当性すら、どうでもいいことのように感じてしまう。
とはいえ。
はたして爪のない彼女は、本当にどうなってしまうのだろう?
目をくり抜かれても、乳を切りとっても、彼女は生きていけるに違いない。
しかしあの爪だけは。
美しく、まるで我が身を守るための懐刀のように鋭い。
あの爪だけはダメなのだ。
それこそが彼女の生きる活力であり。
智慧であり、精霊であり。
すべてであるのに違いないのだから。
少なくとも私はそう信じている。
*
いよいよ彼女の手の話をしよう。
ある日、私はとても奇妙な夢を見た。
そこには見知らぬ女がいた。
現実ではたしかに見知らぬはずの女。
しかし夢の中の私はその女と知り合いなのだ。
そこは女の私室のようだ。
女は鏡の前で化粧をしている。
私はヴェルヴェット・アンダーグラウンドを読んでいる。
読みながら、ちらちらと女のほうをうかがっている。
そして、思わずアッと驚きの声を漏らしてしまった。
女はなんと『彼女の手』で化粧をしていたのだ。
彼女の手でパフパフと。
ファンデーションを顔に塗っていたのだ。
私にはわかる。
それはたしかに彼女の手だった。
背筋が凍りついた。
それは彼女の手であると同時に、間違いなく化粧道具なのだ。
私はなぜかそのことを理解している。
なのに。
どうしても尋ねずにはいられなかった。
「それはなんです? あなたが化粧に使っている、その道具です」
「え、これ?」
鏡の中に、女の微笑が浮かんだ。
振り向いた女は。
それを私の方へ放ってよこした。
私がそれを取り上げてみると――やはり彼女の手だった!
「いったい、これはどうしたんです!」
思わず尋ねながら、私はここ数日、彼女に会っていなかったことを思い出す。
「わかってるでしょ? それは彼女の手よ」
女は平然と答える。
私はその残酷さにゾッとした。
「最近、海外で流行ってるの。知らない?」
知るはずがない。
彼女の手をパフに加工する?
そんな猟奇的なことが、どこでだって、現実に流行るはずがない。
「あなたが作ったんですか?」
「医科大の先生よ。ほら、あなたも知っているでしょう?」
言われてみればそんな気がする。
……たしか。
解剖のあとの死体の首。それを、土の中に埋めて髑髏を作る。
それで怪しい連中と秘密の取引をしている。
と聞いて、とてもイヤな気分がした。
どうしてそんな奴に。
私は女というものの、無神経さや残酷さを憎まずにはいられない。
しかし私は、つぎの瞬間には、こんなことを考えはじめている。
それが海外で流行っていることについて。
自分もそんなことを、テレビか雑誌か、あるいは新聞か何かで。
読んだことがあるような気がするのだ。
猟奇的なことというのは、いつの時代のどこの場所でだって。
流行りやすいものではないか?
*
ソファの上でうたた寝していた私を、
『んにゃああん。ふふふ。あなた、本当にあたしのここが好きよね』
彼女がまるで挑発するように起こす。
ああ、なんてやわらかいんだろう。
私は彼女のそれをパフパフと顔に押しつける。
そうしていると――なるほど。
たしかに彼女のそれは人間の化粧道具にもなりそうな気がしてくる。
しかし私にとってそんな化粧道具がいったい何の役に立つだろう?
私はソファの上で仰向けに寝転んで、彼女を顔の上にあげる。
彼女のやわらかいそれをやさしくつかんでまぶたにあてがう。
心地よい彼女の重み。
それは、あたたかく、やわらかく、とても気持ちがいい。
ぷにぷに。
私の疲れた眼球に、しみわたっていく。
ぷにぷに。ぷにぷに。
しみじみとした、まさにこの世のものとは思えない安息。
ぷにぷに。ぷにぷに。
ぷにぷに。ぷにぷに。
彼女もきっと気持ちいいに違いない。
ぷにぷに。ぷにぷに。ぷにぷに。ぷにぷに。
ぷにぷに。ぷにぷに。ぷにぷに。ぷにぷに。
ああ、すばらしきかな、この肉球!
仔猫よ!
お願いだからしばらく踏み外さないでくれよ。
お前はすぐ爪を立てるのだから。
<おわり>
※
読んでいただきありがとうございました。
※オリジナル小説は、【狐人小説】へ。
※日々のつれづれは、【狐人日記】へ。
※ネット小説雑学等、【狐人雑学】へ。
※おすすめの小説の、【読書感想】へ。
※4択クイズ回答は、【4択回答】へ。
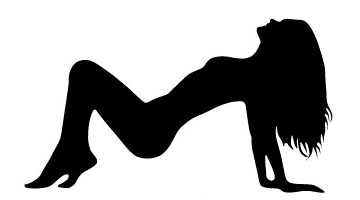

コメント