狐人的あいさつ
コンにちは。狐人 七十四夏木です。
読書していて、
「ちょっと気になったこと」
ありませんか?
そんな感じの狐人的な読書メモと感想を綴ります。
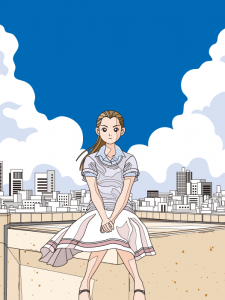
今回は『きりぎりす/太宰治』です。
文字数13000字ほどの短編小説。
狐人的読書時間は約34分。
貧乏画家の夫が成功した途端天狗になる。妻はそれに嫌気がさす。俗物化した夫を痛烈に非難し別れを一人語る。反俗精神は概ね理解できる。だけどそれをひとりよがりだと感じてしまう僕は……
未読の方はこの機会にぜひご一読ください。
狐人的あらすじ
『おわかれ致します。あなたは、嘘ばかりついていました。』――とある女性が、五年連れ添った夫に、別れを告げる、一人語り。
夫は売れない貧乏画家だった。女性はその絵を見て強い衝撃を受ける。どうしても、あなたのとこへ、お嫁に行かなければ、と思う。
そもそも女性がその絵に興味を持ったのは、父親の会社にその絵を売りにきた骨董屋が、ぶしつけに画家との見合い話を持ち出してきたからだった。
両親はひどく反対したが、女性はほとんど身一つで、その画家と結婚する。夫は、展覧会にも、大家の名前にも、てんで無関心で、勝手な絵ばかり描いていたが、女性はその高潔な生き方を愛す。
暮らしは大変貧しかったが、女性は貧乏を楽しんでいた。たとえ一生貧しくとも、他人に迎合せず、一生俗世間に汚されずに過ごしていくであろう夫を、生涯支えていくつもりだった。
しかし、そんな女性の思いとは裏腹に、夫の絵はだんだんと高い評価を得て、飛ぶように売れるようになる。
富と名声を得るにしたがって、夫の性格が変わっていく。
コネづくりの挨拶回りに余念がなく、家ではそれら大家の陰口を平気でたたき、金に汚くなり、他の絵の批判ばかり、表ではひとにいい顔をして、裏ではそのひとの悪口をいい、お世話になってきた骨董屋にまで悪態をつく始末――どっぷり俗世間に染まってしまったのだ。
そして、夫が俗世間に染まっていくほど、その富、地位や名声は揺らぎのないものになっていく、みるみる出世していく……。
女性は五年経ったいま、夫を軽蔑し切っている。こんなに長い別れの文句を語ってしまうほどに。
だけど、世間において、夫のいまの生き方こそが正しいのだと、自分の考えこそが間違っているのだと、女性にはわかっている。が、その考えのどこがどう間違っているのか、女性にはどうしてもわからない。
寝床に入った女性の背筋の下、縁の下でこおろぎが鳴いている。その鳴き声を聞くと、女性の背骨の中で、きりぎりすがひっそり鳴いているような気がする。
その小さい、幽かな声を、女性は背骨にしまって、生きていこうと思っている。
狐人的読書感想
女性の言っていることのあらましは、つまり反俗精神。
言っていることはわかるのですが、自分だけの勝手な想いを男性に押しつけ、その理想とするイメージと変わってしまったからといって、夫に幻滅し、軽蔑し、別れの言葉とともに痛烈な批判を綴っていて――なんだか自分勝手だなあ、なんて、思ってしまうのはひょっとして僕だけ?
夫は俗世間に媚びたりしない、孤高の天才芸術家、彼の絵をわかるのは自分だけで、だからどんなに貧しくても、自分が一生支えていくんだ――って、たしかに男にとってはありがたく、得難く、立派な伴侶だという気がするのですが、だけど自分の独占欲とか、悲劇のヒロインであることに酔うナルシシズムとか、まったくないとは思えないんですよね。
そのために、世俗に迎合しない、孤高の天才画家という理想像を、勝手に夫と重ね合わせて見ていて、夫の人格を思い込みで固定してしまっているところに、ちょっと違和感を覚えてしまいます。
でも、女性は結婚当時19歳で、手紙を書いているいまでも24歳ですからね……、異性を理想化して、自分をヒーローやヒロインに見立てて恋に酔いしれてしまう、というのはわかるような気がします。
野心や功名心のない人間なんて、ほとんどいないのではないでしょうか。とくに芸術家、創作をするクリエイティブなひとというのは、多かれ少なかれ自分の作品を誰かに見てもらい、評価を得たいという思いが強いはずです。
インターネットの普及により、いまでは誰でもネット小説を書いて簡単に公開できるし、SNSを見ていても、自作の絵をあげているひとは多いように感じます。
自分だけが満足するために創作をしている、なんてひとは、やっぱりほとんどいないんじゃないですかね、なんて考えてしまいます。
もちろん、本気で小説や絵で食べていこうとしているわけじゃなくて、趣味としてやっているというひとは多く、そういうひとたちはお金や名声なんてさほど求めていないのかもしれませんが、しかし本作の画家の場合は、明らかに絵だけを描いて生活しようとしていますよね。
芸術家の孤高であったり、世俗を拒絶しているような態度って、結局のところ、諦観とか自己防衛とか、何かしらマイナスの気持ちから生じているのが普通だと思うんですよね。
すなわち、程度の差こそあれ、俗世間に染まらぬ仙人のような人間なんて、いないのではないでしょうか?(年齢にもよるでしょうか? もちろんプライドなどの例外となる気持ちとかもあるのでしょうが)
誰かに認めてほしい、評価してほしい、作品を買ってもらって、有名になりたい――芸術家にそんな思いがないほうが不自然で、なぜ女性がそのことに思い至らなかったのか、夫だけは俗世間に染まらない孤高の芸術家だと思い込んでしまったのか……、狐人的にはとても不思議な気がします。
もちろん「恋は盲目」の一言で片付けてしまうことは可能ですが、そうなってくると、恋は盲目してしまったのは明らかに女性の過失なので、画家として成功した夫が多少天狗になってしまったからといって、ここまで辛辣に非難されてしまうのは、なんだかかわいそうに思いました。
――とはいえ、夫の天狗っぷりは「多少」ではすまされない増長っぷり……、であることは、女性の手紙を読むかぎりでは、認めないわけにはいきません。
お金持ちになって、いい家に住んだり美味しいものを食べたりするのは、べつに悪いことだとも思いませんが、ひとの悪口を言ったり、お世話になってきた骨董屋さんにまで横柄な態度をとるようになったり、妻を裏切るような夜の遊びであったり――女性がああ言いたくなる気持ちもわかります。
人間、おだてられればどこまでも昇ってしまうもので、辿り着いた高みからついついひとを見下してしまう、というのは想像しやすいように思います。
これまであまり褒められたことのないひとならば、なおさらそうなのではないでしょうか?
僕もこの点、他人事ではないかもしれないな、なんて考えてしまいます。
自分が偉くなったと実感したとき、天狗にならないのは難しくかんじられます。
また反対に、自分がおちぶれてしまったと実感したとき、ひとは卑屈にならずにはいられません。
刑務所に入れられた富者、権力を手にした貧者――人間は置かれた立場や環境で、がらりと態度が変わってしまい、どこでもきれいに咲く睡蓮のように、いつでもどんなところでも高潔でいることは、非常に難しく感じられます。
僕も普段テストの点がよかったり、お腹が空いていたり、イライラしていたり――たったそれだけのことでも、ひとを見下してしまったり、ひとに冷たい態度をとってしまうことがあり、女性の夫のような突然の出世を経験したとき、天狗にならないとは正直断言しがたいところがあるんですよね……。
思えば、そのことが頭の片隅にあったから、女性の言うことすべてに賛同することができなかったのかもしれません。
天狗になった夫の擁護みたいな感想になってしまったのは、天狗になり得るかもしれない僕自身のための擁護だったのかもしれず、なんとなく恥ずかしいというか、反省すべきことのように感じています。
しかしながら、自分が成功している姿なんて、どうしても思い浮かべることができず、僕には無縁な話かなあ、なんて感じも持ちます。
とはいえ、ふとしたきっかけで増長してしまうことは、日常のあらゆる場面に潜んでいることだと思ったので、そんなとき『きりぎりす』の小さい、幽かな声を、ぜひ思い出したいと思いました。
読書感想まとめ
この女性の言っていることを、すべて受け入れることができなかったのは、自分も成功した夫のように、天狗になる可能性が、頭のどこかにちらついていたからかもしれません。
とはいえ、女性の言っていることも、やっぱり間違っているとは言いがたく、俗世間の正しさと反俗精神の正しさと、どちらが間違っているのか――というあたりの葛藤は、とても共感できるところでした。
自分が増長してるな、って感じたとき、ふと、きりぎりすの小さい、幽かな声を思い出し、その態度を改めることができたらいいな、と思いました。
狐人的読書メモ
・『きりぎりす』というタイトルについて。なぜ女性は自分のことをきりぎりすにたとえたんだろう? きりぎりすといえば『アリとキリギリス』の怠け者のキリギリスのイメージが強い。なんだかんだで自分の絵を描き続け、俗世間と融和し、認められていく夫に対し、自分の悩みや苦労などはなんということもないのかもしれない、という秘められし想いの表れなのか……興味深く思う。
・『このとしになっては、どこがいけないと言われても、私には、もう直す事が出来ません。』――年々、頑固というか意固地というか、そうなっていく自分を感じる。成長に伴う自我の定着は当たり前のことではあるが、柔軟な部分を失いたくないと願いつつ、あるいはすでにもう失われているのかもしれない。
・『私でなければ、お嫁に行けないような人のところへ行きたい……』――こういうことは考えたことがなかった。現代の世間一般の女性はどうなのだろうと興味が湧いた。
・『この画は、私でなければ、わからない……』――一つの絵を見て、そういうふうに感じられる感性はすばらしいと思ったけれども、そこにひとりよがりなエゴをも感じた。
・『だって、お金の無い時の食事ほど楽しくて、おいしいのですもの。』――こういう考え方ができるのはすてきだと思った。
・『……私は自身が何だか飼い猫のように思われて、いつも困って居りました。』――夫にやさしくされてこんなふうに戸惑うのは独創的だと感じた。それとも一般的な感じ方なのだろうか?
・『こんなに、いい事が、こんなに早く来すぎては、きっと、何か悪い事が起るのだとさえ、考えました。』――これは共感しやすいと思う。突然の幸福に、人は喜びばかりではなく、不安をも覚えるものだろう。
・『所詮は生涯の、女房なのですから。』――夫の浮気を肯定しているのか、あるいは諦観なのか……、とても心に残ったフレーズ。
・お金持ちになると人は変わる。だけど、お金持ちになった人の周りの人たちもまた変わる。お金がなくなれば人は離れていく。変わらない人間関係なんてあるんだろうか? 良い方向に変わっていく人間関係だってあるんだろうか。
・人の受け売りばかりで、自分の意見を持っていないような夫の姿は、非難されてしかるべきなのかもしれないけれど、なんだかさびしさのような感情も覚える。ふとパクツイのことを思い浮かべる。
・『いい画さえ描いて居れば、暮しのほうは、自然に、どうにかなって行くものと私には思われます。いいお仕事をなさって、そうして、誰にも知られず、貧乏で、つつましく暮して行く事ほど、楽しいものはありません。私は、お金も何も欲しくありません。心の中で、遠い大きいプライドを持って、こっそり生きていたいと思います。』――たしかに高潔な生き方だと思う。そんな生き方ができればいいなと思う。だけどそれぞれの人格や事情――現実にそれができる人は少ないとも思う。
・芸術の世界において、一度名声を得れば、その後の作品の出来ばえに関係なく、名は高まっていくことを思う。それがコネなどという、俗世間的なことなのかもしれない。たしかに汚いことのようにも感じられるが、それをも含めて才能なんだろうか……、スポーツの世界などでも同じようなことがいえる。
・『きりぎりす/太宰治』の概要。1940年(昭和15年)『新潮』にて初出。一人語り、あるいは書簡体形式。簡単にいえば、成功して天狗になってる夫を嫌いになっちゃう話。この女性の言っていることはおおむね理解できるが、ところどころに違和感を覚える。今回の読書感想は、俗物化した男を非難する女性を、非難的に見つめることで、自分自身の内面をとらえてみようとしてみたけれども、うまくいっているかはわからない。
以上、『きりぎりす/太宰治』の狐人的な読書メモと感想でした。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
(▼こちらもぜひぜひお願いします!▼)
【140字の小説クイズ!元ネタのタイトルな~んだ?】
※オリジナル小説は、【狐人小説】へ。
※日々のつれづれは、【狐人日記】へ。
※ネット小説雑学等、【狐人雑学】へ。
※おすすめの小説の、【読書感想】へ。
※4択クイズ回答は、【4択回答】へ。


コメント